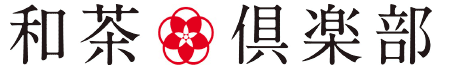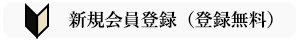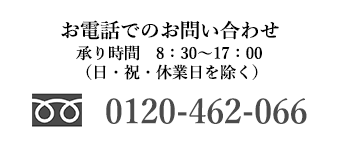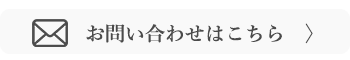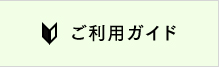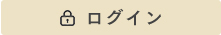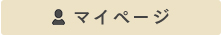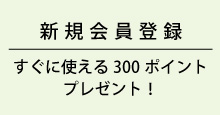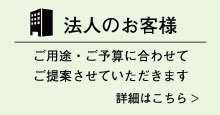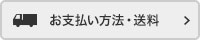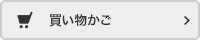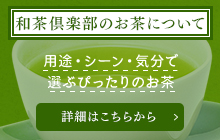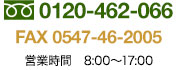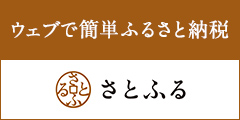福建省安渓県で作られたお茶を紙で包んだことから「包種茶」と呼ばれるようになる。
緑茶に近い浅い発酵度である。
一芯二葉または一芯三葉で摘み、春茶(3月中旬から5月上旬)と冬茶(10月下旬から11月中旬)
の評価が高い。揉捻は細く長く仕上げる。
茶葉の色は深い緑、蘭の香りが清く、高く長く香る。喉ごしが良くあと味が甘い。水色は、
透明感のある黄緑である。
文山包種茶(ぶんざんほうしゅちゃ)
富丁茶(ふていちゃ)
「苦丁茶種」というが、茶木ではない。広東省で好まれ、最近は全国的に広がっている。
紫紅の柔らかな芽、葉を摘む。銘茶の中で唯一茶葉ではない。葉の色は、黒くツヤがあり、
細長い。薬用ニンジンの味に近く、初めは苦いがあと甘くなる。水色はオレンジ色がかった緑。
普陀佛茶(ふだぶっちゃ)
普陀山で産することからこの名になり、普陀山は中国の仏教四大名刹の一つである。
日本の煎茶普及のきっかけを作った隠元も、この寺で修行をした。
一芯一葉または一芯二葉で、清明節の3~4日後に摘む。茶葉の特徴は、白毫があり
黒みがかった緑色。水色は淡い黄緑。
日本の煎茶の味、香りに共通性がある。
茯磚茶(ぶくたんちゃ)
古くは「湖茶」と呼ばれ、伏天(暑い時)に作られるので「伏茶」、加工地の涇陽でつくられるので
「涇陽磚」とも呼ばれる。
茶葉を型から出したあと、発酵させた後、乾燥させるのが特徴である。35cm×18.5cm×5cmのレンガ。
1つ約2kg。黒い茶色をしている。純な香りといわれ、芳醇でボディのある味。水色は、
赤みがかった明るい黄色。濁りがなく、何煎も可能である。
福州茉莉花茶(ふくしゅうまつりかちゃ)
福建省などで、緑茶の荒茶を入れ、福州で産する質、種類において豊富な茉莉の花の香りを
吸着させている。(ジャスミンは茉莉の総称)吸着させる茶葉の質により、またいんの回数の多
さによって高級茉莉花茶となる。代表的なものに「茉莉大白毫」「茉莉銀毫」「茉莉春風」
「雀舌毫茉莉花茶」がある。
良いものは、春の新芽で摘み加工する。4、5煎入れても香りが残る。
武夷肉桂(ぶいにっけい)
肉桂の茶樹は、武夷山あるいは馬振峰で発見され、シナモンの香りがすることからこの名称
になったという説がある。
茶木は2m以上になり、葉は長めの楕円で肉厚である。茶葉は、ツヤがあり黒ずんだ緑色。
4、5煎でも残香があり、果実・乳の香りがする。水色は、透明なオレンジ系の黄色。
磐安雲峰(ばんあんうんぽう)
磐安は「茶経」にでてくる東白茶の茶区の一つである。
4月下旬から5月初めにかけて、一芯一葉または二葉で摘む。芽は肉厚である。
「三緑一香」と呼ばれる。三緑は、茶葉の色・水色・お茶をだしたあとの茶葉の色のこと。
一香は、菊の花の香りを指している。
白鶏冠(はっけいかん)
明代から有名で、武夷四大岩茶(大紅袍・鉄羅漢・水金亀)の一つである。
葉は鶏のトサカのように上向きに巻くように曲がり、光を放っていたことから名づけられた。
5月中旬ごろ二葉または三葉の状態で摘む。発酵は岩茶の特徴である葉が3割程度紅色に
変色する「三紅七緑」である。最後に数度の焙煎をして仕上げる。
白琳工夫(はくりんくふう)
白琳で産することでこの名が付けられた。1900年前後、大白種の柔らかな芽を使い紅茶を
作り始めた。柔らかな芽、葉を摘む。
茶葉は、産毛があり紅色がかった黒色、細長く曲がっている。
新鮮で甘い味、産毛の甘い香り(毫香)がするといわれる。水色はオレンジがかった紅色。
白牡丹(はくぼたん)
1920年代前後に建陽市で作られ、その後政和県でも生産されるようになった。
政和大白種、福県大白種、水仙が使われている。緑の葉の中の白い芯が花のような形から
この名になった。
一芯二葉で春茶のみで摘む。芽、一葉、二葉とも白い産毛があることから「三白」と言われている。
茶葉は白毫も見え、深いコケのような緑色。味は芳醇、渋みは少なく、まろやかである。
水色は、オレンジがかった透明感のある黄色である。