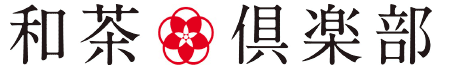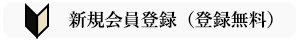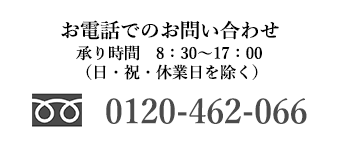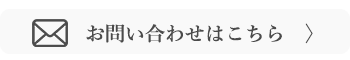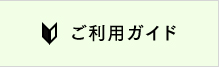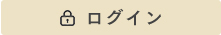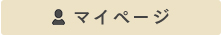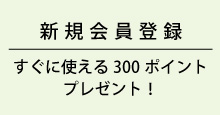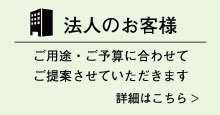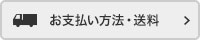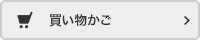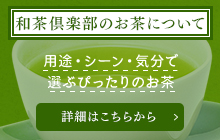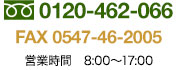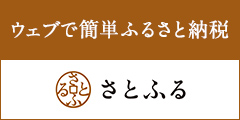1920年代前後に建陽市で作られ、その後政和県でも生産されるようになった。
政和大白種、福県大白種、水仙が使われている。緑の葉の中の白い芯が花のような形から
この名になった。
一芯二葉で春茶のみで摘む。芽、一葉、二葉とも白い産毛があることから「三白」と言われている。
茶葉は白毫も見え、深いコケのような緑色。味は芳醇、渋みは少なく、まろやかである。
水色は、オレンジがかった透明感のある黄色である。
中国白茶
- これより下にカテゴリはありません
白牡丹(はくぼたん)
白毫銀針(はくごうぎんしん)
1880年代に政和大白種が開発され、現在も福県大白種、政和大白種で作られている。
一芯一葉または一芯で摘まれ、明前で摘む春の最初の太い芽が最適とされる。摘んだ後、
風通しのよいところで弱い日光に晒す。荒茶は「毛針」ともいわれる。
茶葉は、芽が太く、産毛で覆われまっすぐで針のようである。味は新鮮で芳醇、香りはたつ。
水色は透明感のある薄い黄色。産毛がお湯に溶けだし、キラキラ輝くのが特徴である。
壽眉(じゅび)
香りは澄んだ感じで、芳醇で爽やかな味をしている。水色を透明感のある薄い黄色をしている。お茶を出したあとの茶葉は緑色をしている。葉脈や周囲が少し紅色になっている。
上質なものになると白毫があり、一般的に発売されているものは、緑色と白毫が混じり合っているように見える。