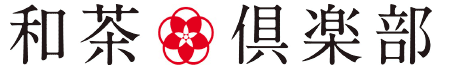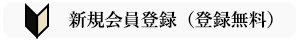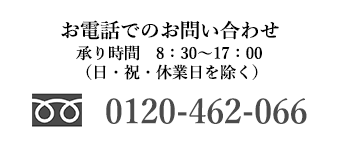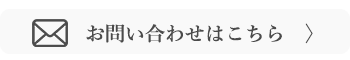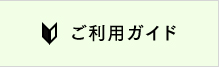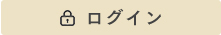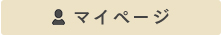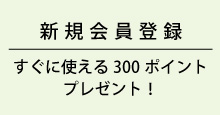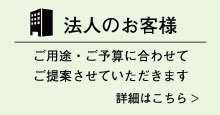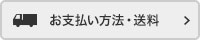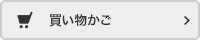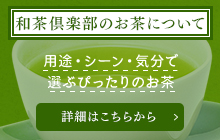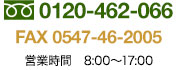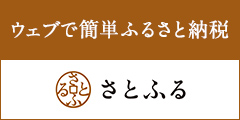福建省武夷山のお茶をもとに、台北近くの文山茶区で最初に作られた。青茶の中で、
もっとも完全発酵(紅茶)に近いお茶である。
柔らかな芽の一芯二葉で摘み、ウンカ(小さな昆虫)が芽を噛むことで独特の味、香りに
なるといわれている。
茶葉の特徴は、白毫があり細く揉捻され、大きく自然に曲がっている。
味は柔らかく甘い、香りは熟した果実または、蜂蜜の香り。水色はオレンジがかった琥珀色。
白毫(香嬪)烏龍茶(はくごう〈シャンピン〉ウーロンちゃ)
白毫銀針(はくごうぎんしん)
1880年代に政和大白種が開発され、現在も福県大白種、政和大白種で作られている。
一芯一葉または一芯で摘まれ、明前で摘む春の最初の太い芽が最適とされる。摘んだ後、
風通しのよいところで弱い日光に晒す。荒茶は「毛針」ともいわれる。
茶葉は、芽が太く、産毛で覆われまっすぐで針のようである。味は新鮮で芳醇、香りはたつ。
水色は透明感のある薄い黄色。産毛がお湯に溶けだし、キラキラ輝くのが特徴である。
白芽奇蘭(はくがきらん)
清代・乾隆年間に、平和県大芹山にある茶木の、新芽が白緑で、蘭の香りがすることから、
この名が付けられた。現在も半発酵茶で、柔らかな芽で作る。
茶葉はツヤがあり黒みがかった深い緑色である。あと味が甘く、清い蘭の香りがし、
高く続く。水色は透明感のある少し赤みを帯びた黄色。
白雲毛峰(はくうんもうほう)
1950年代以降に白雲山で作られたお茶である。
一芯一葉または一芯二葉で、穀雨前後に摘む。
茶葉は、細く産毛があり、色は黒みをおびた緑色である。味は、新鮮で芳醇である。
あと味は甘く、柔らかな香りは長く続く。水色は透明で薄い黄緑。
寧紅工夫(ねいこうくふう)
もっとも古い紅茶の一つである。清の道光初年(1821年)には「寧州紅茶」と呼ばれていた。
一芯一葉で清明節前後に摘む。これは高級茶になる。
葉の特徴は、光沢があり黒っぽい赤色でツヤがある。上質なものには金毫がある。
ボディがある芳醇な味は、あと味も甘い。香りが高く、長く続く。水色は柔らかで、
ツヤのある紅色である。
南京雨花茶(ナンキンうかちゃ)
1950年代後半に作られ南京の雨花台にちなんで名づけられた。
基本的に一芯一葉で清明節の前後に摘まれる。
茶葉は、針のように細く揉まれ、尖っているのが特徴である。味は新鮮で芳醇。
香りは上品で濃い。水色は透明感のある黄緑である。
屯緑(とんりょく)
現在の黄山市周辺で作られたお茶。屯渓緑茶の略である。
茶葉は細く尖り、黒みがかった緑色でツヤがある。あと味が甘く、栗の香りが特徴。
水色は黄緑である。
東白春芽(とうはくしゅんが)
東白山で産するので、この名がつけられた。
一芯一葉または一芯二葉で清明節から穀雨の間に摘む。
茶葉の特徴は、産毛があり白みがかった緑色で、蘭の花に似ている。
味・香りは、芳醇で新鮮、栗の香りや蘭の香りにたとえられる。水色は澄んだ黄緑。
凍頂烏龍茶(とうちょうウーロンちゃ)
凍頂山で産することから名づけられ、台湾を一番に代表する烏龍茶だったが、最近では
高山烏龍茶にその地位を譲っている。
一芯二葉で摘まれる。春茶は4月下旬~5月、冬茶は11月~12月上旬に摘まれ、冬茶葉は
甘く、評価も高い。半休形に強く揉捻される。
以前は焙煎をしていたものも多かったが、最近では焙煎をせず「清香」のものがほと
んどとなった。
東山碧螺春(とうざんへきらしゅん)
太湖の東洞庭山で摘まれるものが最上とされる。茶畑ではなく、梅、桃、柿、杏などの
果物畑で、果樹の下に茶木が植えられている。
100gに8千~1万5千の茶葉があるといわれ、細かくタニシのように曲がっていることから、
この名になった。
基本は一芯一葉で、春分から穀雨までに摘み、明前が最上とされる。