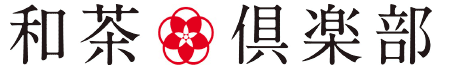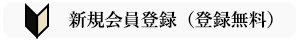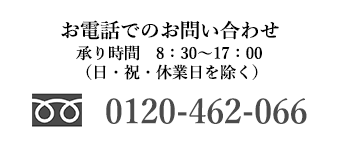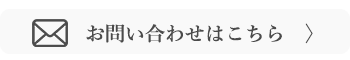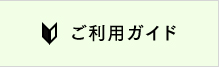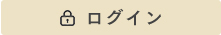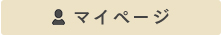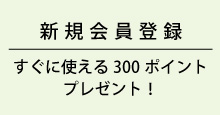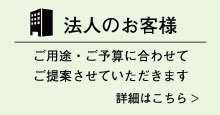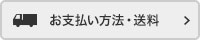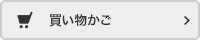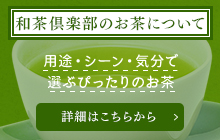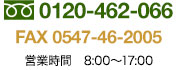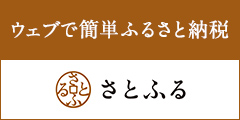上質の茶葉は、一芯一葉で摘まれ、一芯二葉となると等級が下がる。
葉は細長く、ツヤがあり深緑色である。
味・香りは、清く高く香り、長く続き、あと味が甘く芳醇である。
水色は、明るい山吹色で、出したあとの茶葉も柔らかな緑色をしている。
峡州碧峰(きょうしゅうへきほう)
休寧松蘿(きゅうねいしょうら)
松蘿山は黄山の南麓で産するので名づけられた。
基本的に一芯二葉または、一芯三葉で穀雨の前後に摘む。
炒るときに、釜の横で一人が扇子で風を送り、熱気をとばして、黄色にならない
ようにする工程が特徴である。
茶葉は、ツヤのある緑で柔らかな中国産オリーブのような香りがし、味は濃い。
鳩抗毛尖(きゅうこうもうせん)
千鳥湖の湖畔の淳安県鳩抗郷で産するのでこの名がつけられた。
明前に一芯一葉を基本に摘み、板の上で両手で柔らかく揉む。
葉は深緑で、まっすぐである。水色は透明感があり、柔らかな黄色。
味・香りは、濃く、清らかで長続きする。
祁紅(きこう)
中国を代表する紅茶であり、世界三大紅茶の一つである。
夏茶は評価が高く、一芯二葉または、一芯三葉で摘む全発酵茶のこと。
茶葉はツヤのある黒色で、水色は、透明感のある鮮やかな赤色。
祁門紅茶・・・とも言われる。
官庄毛尖(かんしょうもうせん)
強い揉捻で細く仕上げている。
飲んだあと、爽やかで香りが長く続くのが特徴であり、水色は緑がかかった
山吹色。茶葉の色は深い緑色をしている。
峨眉竹葉青(がびちくようせい)
竹の葉に似た青みのある茶葉であることから名付けられた。
水色は、明るく、清い黄緑色。
一芯一葉または、一芯二葉で摘み、茶葉の大きさがそろっているのが特徴であ
る。爽やかで、味は濃く、芳醇。
峨眉峨蕊(がびがずい)
古くからの銘茶の産地である峨眉山で採れ、花の芯のような形をしており、
峨蕊と名づけられた。白芽、雲芽、雪芽などともいわれていた。
芽だけを摘んだのちすぐに製茶する。炒り、揉捻を数回行う。
九曲紅梅(きゅうきょくこうばい)
西湖周辺の代表銘茶のこのお茶は、一芯二葉で摘み、全発酵させる。
水色は名前の通り紅梅のような鮮やかな紅色で、味、香りはさらりとしていて、上品で、甘い酸味がするのが特徴。
龍のように曲がった茶葉が特徴のこのお茶は、別名「九曲烏龍」とも呼ばれている。現在は西湖周辺で生産されているが、昔は杭州で生産されていた。
鳩抗毛尖(きゅうこうもうせん)
葉は深い緑で白毫があり、水色は透明感のある、やわらかな黄色。香りは、清らかで長続きし、味は濃く、ポディがある、しかもさわやか。また、揉捻に特徴があり、板の上で両手で優しく揉む。
淳安県鳩抗郷で生産されることでこの名がついたこのお茶は、唐の頃、主要銘茶として扱われていた。
休寧松籮(きゅうねいしょうら)
松籮山で生産されるこのお茶は、唐代から生産されており、明代から特に名が広がっていった。
茶葉は緑色で艶があり、中国産オリーブのような柔らかな香りをしている。味はポディがあり、濃い。またこのお茶は「三重」と呼ばれ、色濃く、香り濃く、味も濃いことからきている。
このお茶は炒るとき、釜の横で扇子を使い風を送り、茶葉が黄色にならないように、熱気を飛ばす工程は特徴である。