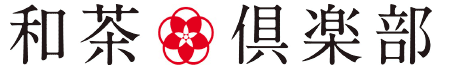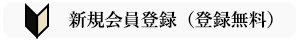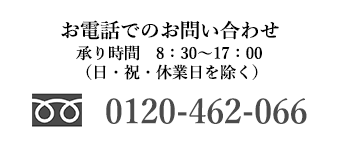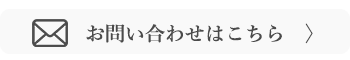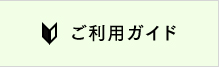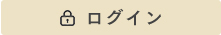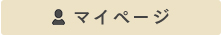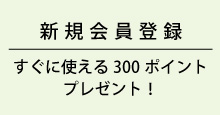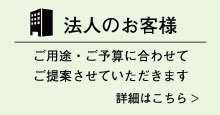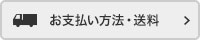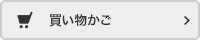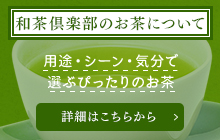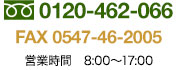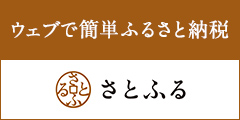茶畑は、浙江省東部、四明山、会稽山、天台山の間に位置する。
一芯一葉または一芯二葉で3月末から4月初めにかけて摘む。龍井茶より少し早めに
摘むが、製法はほぼ同じである。
茶葉は深みのある緑色。味は、爽やかで深みがある。香りは豆の香りに形容され、残香
があるのが特徴的。水色は透明感のある黄緑。
大佛龍井(だいぶつりゅうせい)
大仙峰毫茶(だいせんぽうごうちゃ)
古く「大仙峰名茶」として存在していたが、衰退し1980年代に復興される。
一芯一葉で、早い時期に、柔らかな芽を摘み、啓蟄から春分のあと5日ぐらいで摘み
終わる。
茶葉は、銀毫があり黒っぽい緑色。味は甘く芳醇で新鮮、あと味は爽やかである。
香りも爽やかで長く続く。水色は赤みがかった透明感のある緑。
大紅袍(だいこうほう)
武夷四大岩茶(他に鉄羅漢、白鶏冠、水金亀)の一つで、その中でも伝説的な存在である。
天心岩の九龍窠という岩場に残された4本の茶木をさすが、現在はここから分けられた茶木
からも摘まれる。4本の茶木から摘んだものは、市場にでない。
5月中旬に、二葉または三葉の状態で摘み「三紅七緑」と呼ばれる。葉が、三割程度
紅変する発酵ののち、最後に焙煎される。「岩韻」と呼ばれる残香が魅力である。
双龍銀針(そうりゅうぎんしん)
1980年初めに双龍洞がある地で作られたので、この名称になる。
一芯一葉だが、柔らかな芽だけを摘むのが特徴で、清明前の1週間ほど前から穀雨まで摘む。
殺青から仕上がりまでが40分程度と短い。
茶葉は、白みをおびた緑色で、細くまっすぐ。銀針のような形をしており、白毫がある。
味は柔らかく爽やかで、あと味は甘い。香りは新鮮で爽やか、長く続く。
双井緑(そうせいりょく)
この名称は、双井村の産であることからきている。
宋代以前は蒸す製法の団茶で、宋代以降蒸す散茶となり、現在は炒る散茶となっている。
一芯一葉または一芯二葉で、明前から雨前に摘む。茶葉の特徴は、曲った鳳凰の爪のよ
うで産毛がある。
味は新鮮で爽やか、芳醇でボディがある。香りは清く、高く長く続く。水色は明るい
透明感のある黄緑である。
千島玉葉(せんとうぎょくよう)
千島湖周辺で作られるお茶で、龍井茶に似た作りをすることから、千島湖龍井といった
こともあった。
一芯一葉が基本で、清明節前後に摘む。龍井茶の炒る技術を取り入れている。
茶葉はまっすぐで、産毛があり、黒みがかった緑色である。味は芳醇で濃く、あとあじが
甘い。香りは清く、長く続き、色水は明るく柔らかな緑ないし黄緑である。
川紅工夫(せんこうくふう)
茶葉は、細くまっすぐ揉捻されていて、金毫がるのが特徴である。
色は暗紅色でツヤがあり、味は濃く芳醇、爽やかでボディがある。あと味も甘く、
香り高く、飴の香りがする。水色は、明るく濃い紅色である。
仙居碧緑(せんきょへきりょく)
一芯一葉または一芯二葉で雨前から摘む。複雑な工程はなく、殺青、揉捻、乾燥と
シンプルである。炒る時は、形にはこだわらないが、芽が割れないように気遣いを
する。
茶葉の色は、深い草色で白毫がある。味は、新鮮でさらりとしている。香りは長続き
し、柔らか。水色は、柔らかな明るい黄緑。
宣恩貢茶(せんおんこうちゃ)
一芯一葉で清明節から穀雨の前に摘む。
茶葉は揉捻が強く、細いのが特徴である。色は、黒みをおびた濃い緑でツヤがある。
味は、ボディがあり芳醇で飲んだあとが甘い。香りは清く、長く続き、色水は明るい
黄緑。
雪龍茶(せつりゅうちゃ)
福県大白種など白毫の多い品種を使う。
一芯一葉または一芯二葉で明前から摘み始める。
茶葉は産毛が多く、ツヤがある。色は白みがかった緑。味は濃く、新鮮で芳醇である。
香りは清く長く続き、水色は明るい黄緑。