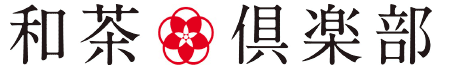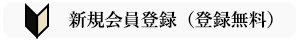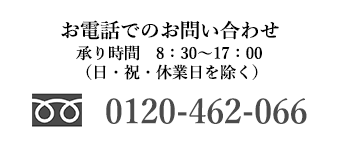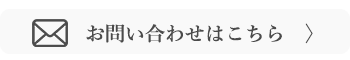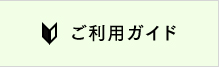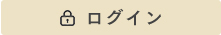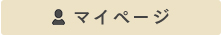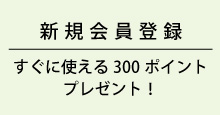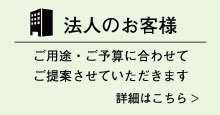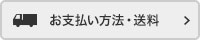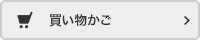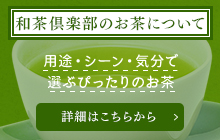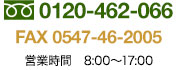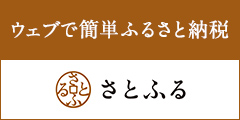清代・乾隆年間に、平和県大芹山にある茶木の、新芽が白緑で、蘭の香りがすることから、
この名が付けられた。現在も半発酵茶で、柔らかな芽で作る。
茶葉はツヤがあり黒みがかった深い緑色である。あと味が甘く、清い蘭の香りがし、
高く続く。水色は透明感のある少し赤みを帯びた黄色。
中国青茶(ウーロン茶)(2ページ)
- これより下にカテゴリはありません
白芽奇蘭(はくがきらん)
凍頂烏龍茶(とうちょうウーロンちゃ)
凍頂山で産することから名づけられ、台湾を一番に代表する烏龍茶だったが、最近では
高山烏龍茶にその地位を譲っている。
一芯二葉で摘まれる。春茶は4月下旬~5月、冬茶は11月~12月上旬に摘まれ、冬茶葉は
甘く、評価も高い。半休形に強く揉捻される。
以前は焙煎をしていたものも多かったが、最近では焙煎をせず「清香」のものがほと
んどとなった。
鉄羅漢(てつらかん)
武夷四大岩茶の中でもっとも古い名木の一つである。名前の由来は、羅漢のように、
樹木の形が壮観で、葉は長く、多くの病を治し、人・世のためになるところからいわれている。
二葉または三葉の状態で摘まれ、葉が3割程度紅色に変色する発酵度「三紅七緑」に
加工される。最後に数度の焙煎をすることで、岩茶独特の甘い残香が出る。
大紅袍(だいこうほう)
武夷四大岩茶(他に鉄羅漢、白鶏冠、水金亀)の一つで、その中でも伝説的な存在である。
天心岩の九龍窠という岩場に残された4本の茶木をさすが、現在はここから分けられた茶木
からも摘まれる。4本の茶木から摘んだものは、市場にでない。
5月中旬に、二葉または三葉の状態で摘み「三紅七緑」と呼ばれる。葉が、三割程度
紅変する発酵ののち、最後に焙煎される。「岩韻」と呼ばれる残香が魅力である。
高山烏龍茶(こうさんウーロンちゃ)
現在、台湾烏龍茶のトップブランドであるこのお茶は、標高1000mを超す茶区で栽培させることからこの名称になった。
1980年代から作られ初め、徐々に開発された茶区で栽培、製茶された烏龍茶であり、包種茶に分類される。4~5月に作られる春茶、11~12月に作られる冬茶がとくにおいしいとされている。
水色は黄金色で、金木犀の花のような香りをしている。味は芳醇で甘く、戻り香が甘いのも特徴である。
漳平水仙茶餅(しょうへいすいせんちゃへい)
大きさは約6㎝四方で外形は、四角い扁平な茶餅で1個約20gであり、使う茶葉は一芯二葉または一芯三葉が基本である。
茶葉の色は艶のある黒っぽい茶色で、芳醇でポディのある味である。水色は、黄色がかった茶色。お茶を出した後の茶葉は、黄色っぽく、葉の周囲が紅色をしている。
水金亀(すいきんき)
大紅袍、鉄羅漢、白鶏冠と並び武夷四大岩茶の一つ。形が亀の甲羅の分様に似ており、葉は濃く茂り、照りがあり光っており、まるで金色の亀のようなところから、この名が名づけられていたとされている。
甘く、上品な香りが特徴的で、5月中旬ごろ三葉の状態で摘まれる。
永春佛手(えいしゅんぶっしゅ)
茶が佛手柑の葉や形に似ていることが名前の由来であるこの茶は、香りは強く、濃く、甘いのが特徴で、水色は透き通るような黄色。
午後摘み夕方製茶を行うもので、春の新芽は紫紅色をしている。発酵は浅めで、揉捻は強い。
1930年代ごろから東南アジアの華僑の間で人気が高まり、1980年代から急速に生産量が伸びた。
安渓鉄観音(あんけいてっかんのう)
20世紀初め、外国の品評会で優勝し、評価が高まった品種である。
茶葉は、細く巻いて重く、肉厚で色重厚、緑も濃く、シルクのような光沢もある。
味は芳酵で、甘く、香りは蜜のようで蘭や金木犀の香りなどに例えられる。水色は黄金色。
安渓色種(あんけいきしゅ)
安渓の半発酵茶の8割を占め、古くから50種を超える半発酵茶が栽培されていたという。
この地域では年五回摘まれるが、その中でも良いとされているのが穀雨から立夏の間、秋分から寒露までの間に摘まれたものである。
簡単に分類すると鉄観音、烏龍、色種の3つに加え、最近黄金桂が加わり4つとなった。
色種で有名な品種は、毛蟹、梅占、奇蘭などがあり、毛蟹は
茶葉がつやのある黒緑色で、香りは甘い花のようであり、水色は黒緑色。梅占は、茶葉が濃い緑黄色、線香の香りが特徴的であり、水色はオレンジのような黄色。